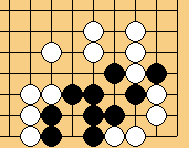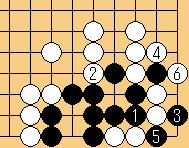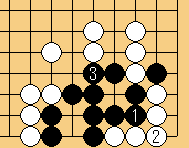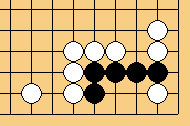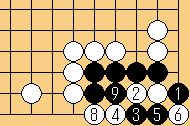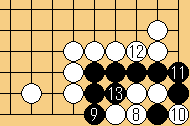今回は詰碁の基本ルールである「後手最強」について説明します。本誌「詰碁世界」の「創作詰碁応募要領」では次のように記しています。
|
後手は地の損得にかかわらず最強の手段で応じる約束になっています。
|
1図 黒先生き
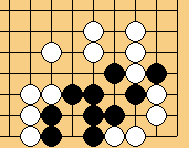 |
2図 後手最強の解
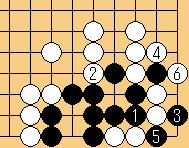
黒7ツギ(5の左) |
3図 後手最善の解
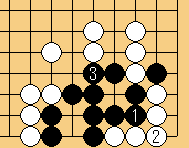 |
1図の詰碁の正解手順が2図ですが、黒3の手筋から黒5の2子取りでは白は大損です。実戦なら3図の白2のツギで黒3の2眼の生きを許すところです。この2図と3図が詰碁と実戦的な死活問題の違いを端的に示しています。詰碁の解答に3図を書いたら×(不正解)にされても仕方ありません。けれども実戦なら(投了の形作りなどを除けば)3図の進行になるのが当然と言えます。
2図が地の損得を問題にしない「後手最強」であり、3図は損得まで考えた「後手最善」であるわけです。詰碁が「後手最強」を基本ルールとするのは、解答者が読み切ったことを示すためと考えられます。
ところが「後手最強」の「最強」という言葉は多分に主観的なものなので、出題者が想定した詰手順(作意)と解答者が示す解答手順が食い違う場合が生じます。そんなとき、出題者が「後手最強ではない」として×にしたりして感情的な問題になることさえあるのは悲しむべきことです。
そこで「後手最強」という概念を定義しておくことが望ましいことになります。第9号の菅原紀明さんの質問に答えたのが以下の定義です。
- 創作詰碁応募要領の原則
手段が最強というのは、無条件かコウかなどの死活の結果で判断されます。本コウとヨセコウなどについては、コウを解決するまでの手数で判断されます。
- 死活の結果が同じ場合の最強の基準
(1) 詰め上がりまでの手数が長いもの
(2) 以降の先手の着手に妙手を必要とするもの
(3) 後手の着手、それ自体が発見困難なもの
|
4図 黒先生き
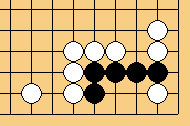 |
5図 4図の解1
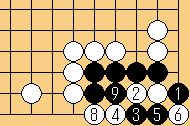 |
6図 4図の解2
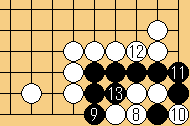 |
4図の詰碁の正解は5図とされている例が多いようですが、手数を考えれば6図の白8の方が最強と言えそうに思います。オイオトシとオシツブシの比較はどちらとも言えないでしょうから。
作図者は解答者がこのような基準で正解手順を選ぶことを念頭におくことが望ましいのです。なるべくなら、変化よりも正解手順の方に妙手が現れる方が作品を観る人に狙いを伝えやすいからです。
コウやヨセコウなどの問題は次回に説明したいと思います。
|