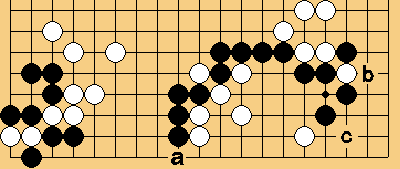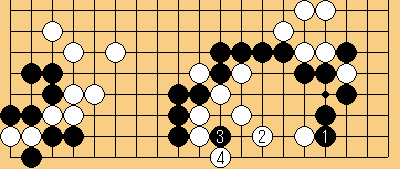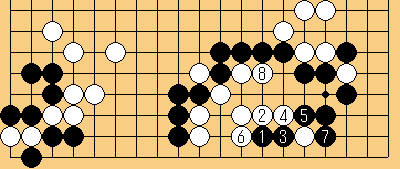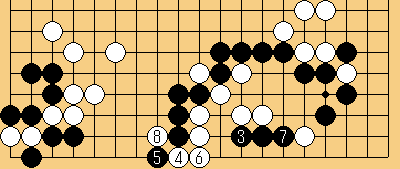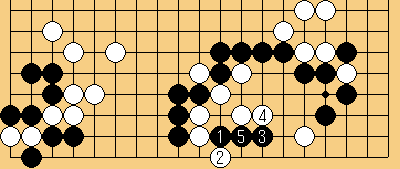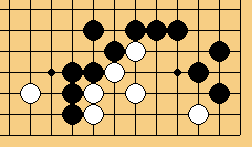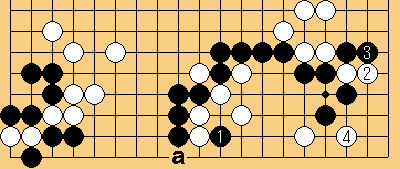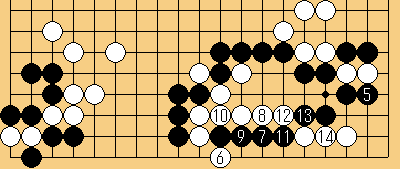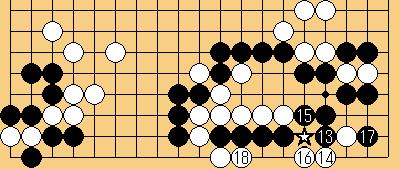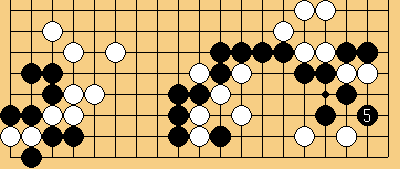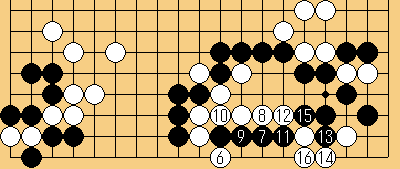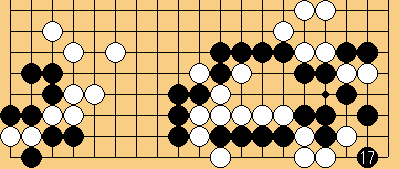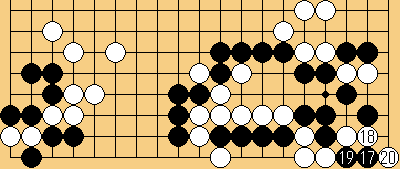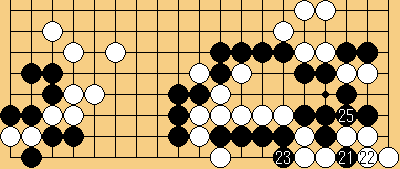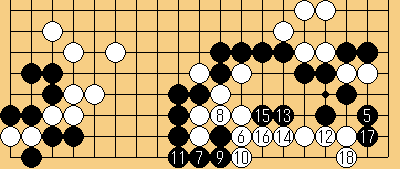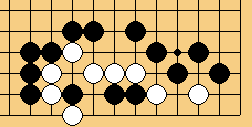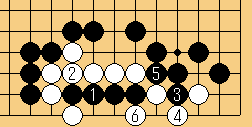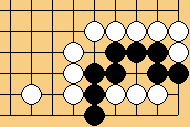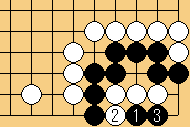何もないところから詰碁を考え出すのは難しいので、実戦に生じた形や既存の詰碁を元にして詰碁を作図することも多いものです。既存の詰碁から新たな詰碁を作る場合は形が変わるのは当然として、実戦形はそのままでは詰碁にならない場合が多いものです。
従って何らかの形の変更が必要なのは通例なので、この作図法を「アレンジ法」と呼ぶことにします。今回は私の実戦に生じた形から詰碁を作図してみます。
1図 実戦形より(黒番)
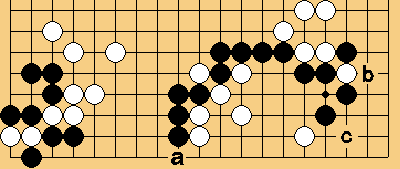 |
黒番で下辺の白を取れるかが問題の局面ですが、白aのハネの具合もありますし、bのサガリから白cの効きもありましたので、全部を取るのは難しい形でした。
まず白cの効きを無視して殺す手段を考えてみます。 |
2図
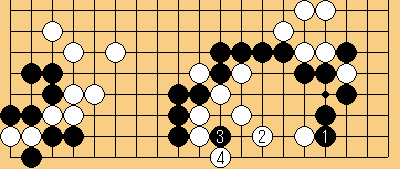 |
この形ですが、黒1には白2でも広そうです。そこで2の所から1の左の白石を取りにいくことを考えます。 |
3図
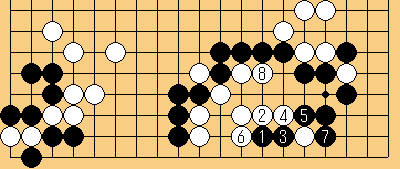 |
黒1から黒5で白の1子は取れますが白6が先手で生きられます。 |
4図
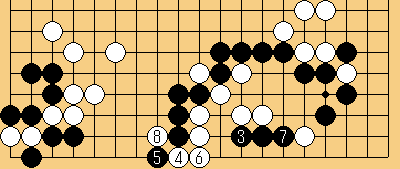 |
黒3と打っても白4のハネで抵抗されタダでは済みそうもありません。 |
5図
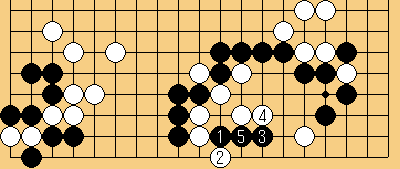 |
そこで黒1が急所になるのです。白2なら黒3から黒5までです。
この筋は詰碁に使えそうです。
白のハネがはっきり効く形にして無駄な石を整理すれば良いのです。 |
6図
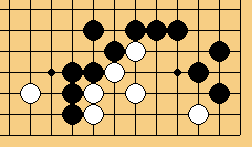 |
本図のように整理すればよいでしょう。これで詰碁が一つ出来たわけです。。 |
7図
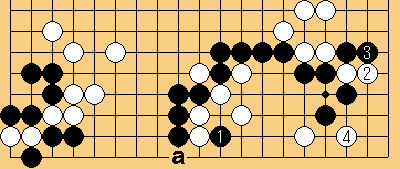 |
黒1では白aのハネ具合を封じられることは分かりました。残るは白2から白4の効きの問題です。 |
8図
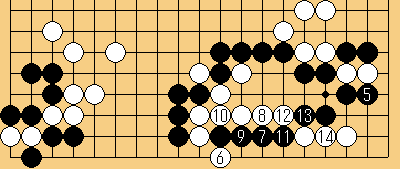 |
黒5と受けることから考えます。
白6以下黒13のときに白14で手数が伸びます。黒4子は3手しかなく、左右の白は4手以上ですから、黒の攻め合い負けです。 |
9図
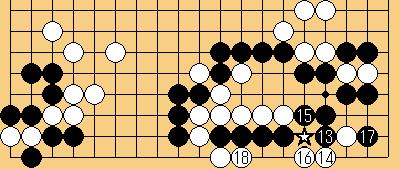 |
ここで白☆を取らなくても黒4子が右方に脱出できれば白を殺せる、と発想を転換できればセンスが良いと言えます。渡り狙いの黒13です。しかし、白14と渡られて、やはり攻め合いは勝てないのです。
本図を読んで、8図の黒5に疑問を持たれた方はお強いと言えます。 |
10図
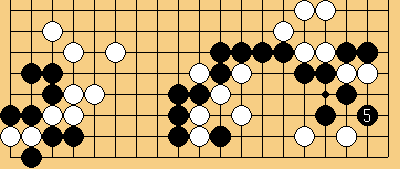 |
8図の攻め合いに備えて、黒5のコスミで頑張るのです。 |
11図
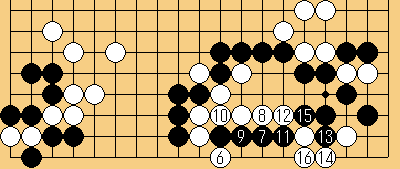 |
白6以下白16までは同じです。 |
12図
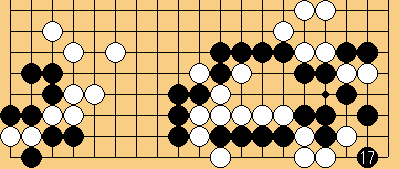 |
ここで、黒17という手筋が成立するのが図10の黒5コスミの効果です。 |
13図
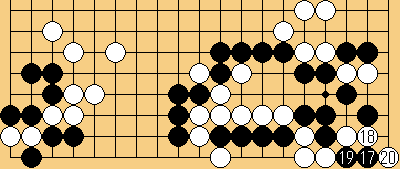 |
白18には黒19と2目にして捨てます。 |
14図
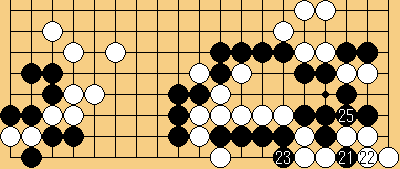 |
再び黒21と捨てて以下は簡単なオイオトシです。
これは凄い手順です。この手順が必然なら、名作の誕生なのですが。
白24ツギ(21) |
15図
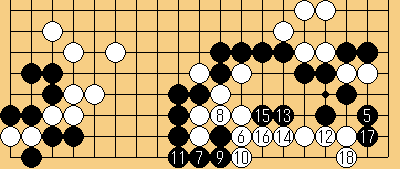 |
実は黒5のとき白6と打つ冷静な手段があって、例えば白18まで、ぴったり生きているらしいのです。 |
7図、10図〜14図は凄まじい「勝手読み」なのですが、それをご披露したのには訳があります。詰碁の創作には、こういう「ひらめき」と「願望」の両方が必要だからです。それがあってこそ、何とか「この筋を詰碁にしてやろう」という意欲が湧いてくるのです。作図は慣れるまでは試行錯誤の連続です。それを支えるのが「筋を成立させた瞬間の感動」なのです。
余詰めはあっては困りますが、検討に自信がなければ公表しなければ良いだけの話です。まずは納得できる筋か形の図を作りましょう。大丈夫そうなら投稿してください。チェックもしますし、手直しのアドバイスもしています。
今回の「勝手読み」も無駄には終わらせないようにしたいと思います。
16図
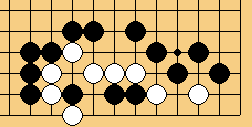 |
これが二つ目の詰碁です。
初手で左方のツギやアタリを打つのは悪手でコウになってしまいます。(17図参照)
これで二つ目の詰碁の完成です。
|
17図
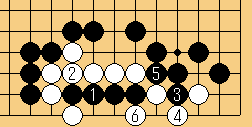 |
黒1を決めるとダメヅマリになり以下黒5のとき白6のハネでコウになります。 |
この「実戦形からのアレンジ法」で作図した拙作を一つ紹介します。
18図 「算月」第7題
「だいじょうぶ」 黒先
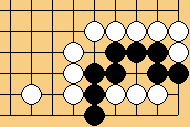 |
19図 18図の解
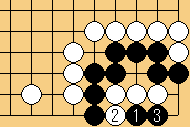 |
見ためよりは広い形ですが、黒1から黒3がしゃれた手筋で無条件生きです。
実戦形を元にしても「勝手読み」というウソをマコトに変えることで、作品と言える詰碁も作れるという実例です。
|